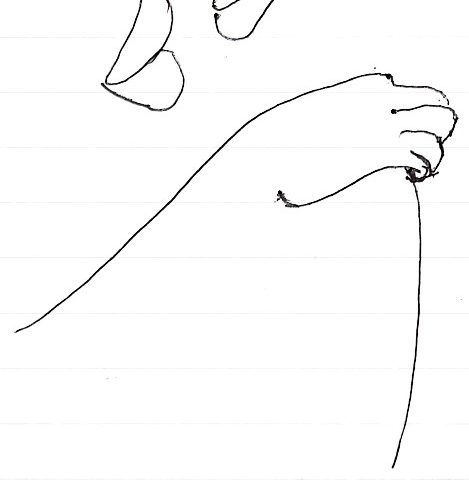特段これといった関係があったわけではない。ちょっとだけ顔見知り、その程度の間柄だった。
十年前に妻を喪ってから、いつの間にか行きつけになってしまった居酒屋でその夜も一人で飲んでいると、彼女が来た。扉口に立った彼女の眼と彼の眼が出会った。笑みを落としてためらいもなく彼の座っている席に彼女は対座していた。
「こんなとこで会うなんて、奇跡のめぐり逢いね」
「どうぞ、飲んでください、好きなもの食べて」
夕方の六時前から彼はここに座っていたが、彼女と一緒に飲みだして気が付けば、九時を過ぎていた。
「カラオケスナックに行く?」
「余りうまく歌えないけど、行きたい!」
ママの他には誰も客はいなかった。新型コロナの騒動以来、客足は遠のいていた。
「最近、少しお客さん、戻って来たけど」
仕方なさそうな顔をしてママはそんな言葉を零していた。
彼の左隣のカウンター席に座り、彼女はウイスキーの水割りを飲んでは右手にマイクを握り続けた。ハスキーな声で時折彼にささやきかけるように歌っていた。彼も歌っては飲み続けた。新たにボトルを追加注文した。
もう何曲目のデュエットかも忘れてしまった。間奏曲に入った時、彼女は彼に向き合って両腕で彼の肩を抱きしめ、上目遣いに見つめた。目もとが少し笑っていた。それは妖しい吸引力だった。彼の中から、ママの姿もテーブルに置かれたウイスキーの瓶やコップ、右手に持ったマイクでさえ既に消えていた。あたりには何もなかった。闇の中で、眼前の唇だけがポッチリ存在していた。制止できなかった。というより、そんなことを考えるわずかな隙間もなかった。狂った歯車で引きつけられるように、ポッチリしたそこに彼の唇が重ねあわされていた。