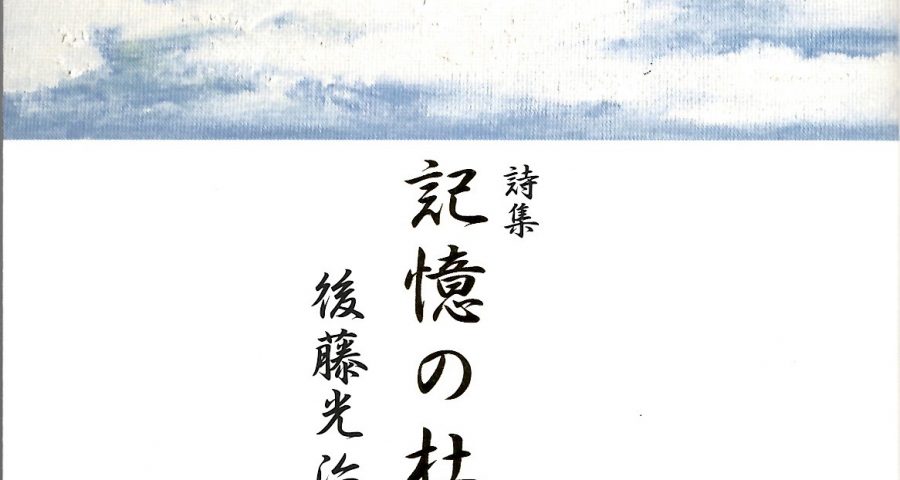現在から過去に向かって、過去といってもそれは半世紀前後かけ離れてしまった場所ではあるが、少年や少女たちが住んでいたその場所をライトで照明して、現在のスクリーンに映像する。そしてその多様性に満ち、余りにも豊かだった世界の映像を言語化する。前置きが少し長くなってしまったが、そんな詩集を私は開いた。
詩集「記憶の杜」 後藤光治著 土曜美術社出版販売 2022年11月20日発行
奥付によると、著者は既に二冊の詩集を出している。第一詩集は二〇一八年、第二詩集は二〇一九年、そしてその三年後に私がいま読み進んでいる第三詩集が出版された。著者はすさまじいスピードで詩集を出版している。しかもこの背後に、個人詩誌「アビラ」を継続して出版していることを思慮するならば、著者の脳裡には、無数の言葉があふれ出ている、そう表現せざるを得ない。
その上、すべての言葉が著者の少年時代、生まれ育った場所、「吹毛井(フケイ)」という村落に向かって帰郷していくのであった。裏を返せば、著者の現在の社会生活の中には、詩は既に失われてしまった、そういう思いをにじませているのだろう。
それはともかく、著者の「記憶の杜」は、ひたすら「吹毛井の記憶群」の言語化だった。例えば、かつて著者の少年時代の「吹毛井」では死者を土葬にしていた。すべての死者が死者のままで村に眠り続けていた。だがある日、この村でも土葬が廃止され、火葬になってしまった。それでは死体が火葬場で焼かれてしまうとどうなるのだろうか。その人は完全に消滅してしまうのだろうか。死者は消滅するのだろうか。著者は、かく問いかける。
頭蓋は灰となるが
記憶は燃えるものなのか(本書105頁)
余談になるが、著者が発行した三冊の詩集すべてが、三部に分かれ、各部に八篇の詩が配置されている。これは単に整合する美しさを表現しようとしているのか。あるいは、三、八、そして八の三倍の二十四、この三つの数字に著者固有の思いがあるのか。それともピタゴラス系の神秘が宿っているのか。
つい多言を弄してしまった。
さて、故郷喪失、帰る場所を持たないという近代人が抱え続けている問題、つまりもっとわかりやすく言い換えれば、私達は真摯に自分を、またこの世界を見つめるならば、人として豊かに楽しく暮らせる場所を既に失ってしまった、驚きの目をもってこの事実を発見するのではあるまいか。この失われた根源への回帰を、著者の三冊の詩集は抒情的リアリズムとでもいえばいいのか、著者独特の言語世界で極めて具象的に明るみへ出さんとしたのではあるまいか。