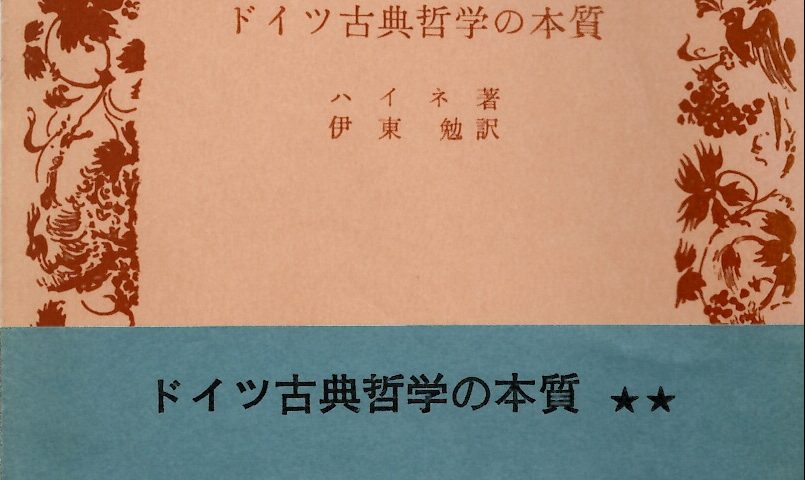最近、フォイエルバッハの本を数冊読んだので、言うまでもなく彼は宗教批判やドイツ古典哲学批判などをやっているが、よし、それならば、私はそう思ってこの本を読んだ。
「ドイツ古典哲学の本質」 ハイネ著 伊藤勉訳 岩波文庫 昭和44年1月20日第14刷
この本は三巻に分かれていて、第一巻は「宗教改革とマルチン・ルター」、第二巻は「ドイツ哲学革命の先駆者。スピノザとレッシング」、第三巻は「哲学革命。カント、フィヒテ、シェリング」。
十八世紀末、フランスではフランス革命によって、封建社会における身分制度の廃絶、それに伴う資本主義的な市民社会の確立への道が拓かれた。しかし、ドイツでは資本主義成立への社会革命では立ち遅れていたが、デカルトに始まる近代哲学やフランス革命の流れの中で、一部の知識人による「宗教・哲学の革命」によって、フランス革命に匹敵する思想の革命が展開された。その辺りをさまざまなエピソードを交えながら、ハイネは興味深く語っている。
詳細は本書に譲るとして、この作品全編に流れるハイネの立っている位置、一言でいえば汎神論的唯物論であるが、以下にその立場のわかりやすい説明文をこの本から引用しておこう。
スピノザが実体とよび、ドイツの現在の哲学者が絶対者とよんでいる「神」は、「この世にげんにあるすべてのもの」である。それは物質であり、精神である。精神も物質もひとしく神である。神である物質をはずかしめる者は、神である精神にそむく者とおなじ罪をおかすことになる。(本書97頁)
私はこの本を読んでから、以前読んだ「世界の詩集第三巻ハイネ詩集」(井上正蔵訳、角川書店、昭和42年2月10日初版)を再読した。この本は亡くなってもうすぐ八年になる妻の高校時代の遺品で、「世界の詩集全十二巻」がリビングにある本棚に勢ぞろいしている。その中から、やはり、この本と同じ立場を表現したハイネの詩を掲げて、この稿を終わる。
聖なる神 神は光の中にもいる
闇の中にもいる
存在するすべてが神だ
神はわれらの接吻の中にもいる(「この岩の上に」最終連、「ハイネ詩集」139頁)