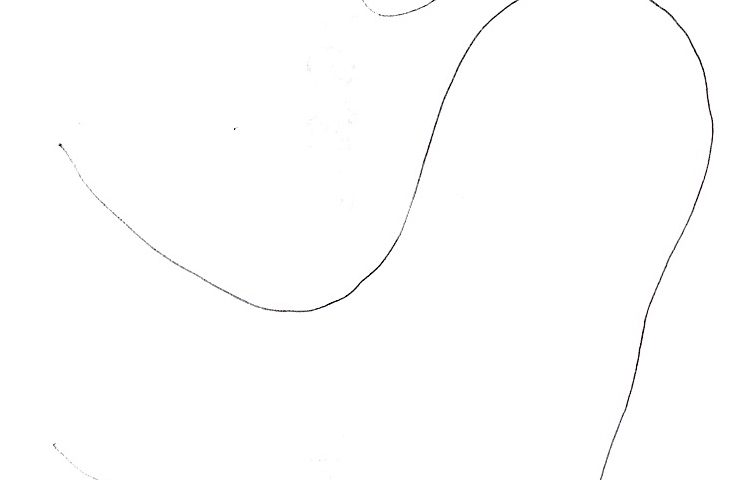この物語は、列車に同席した男性から始まる。いや、それ以前からずっと物語は続いていたようだが、「それ以前」はボンヤリして私にはわからなかった。
男性にはまったく見覚えがなかった。小太りした中年のこの男性は、スーツにネクタイ姿で、やり手のビジネスマンに違いない。私に同行して客先に書類を提出し、担当者と打ち合わせをする、大切な仕事だ、列車の客席に対面して座り、確かそんな会話を交わしたはずだった。
駅に着いた。長い廊下を歩いていくと、吊り橋に出る。向こう岸が見えない大河に架かった吊り橋。空はかき曇り、吊り橋が小刻みに揺れている中を前進する。同行している男性は、吊り橋を支えるためその下部に垂直に設置された幅一メートルにも満たない鉄骨の先端まで、先端といってもおそらく二、三メートルくらいだろうか、そこにしゃがみこんで何やらゴソゴソしている。だが、いつの間にか彼は私の背後にいて、「これで大丈夫だ」、そう呟いている。
前方からは二人の女性がやってきた。一人の女性は、以前、何度も会って笑いながらおしゃべりさえしているはずだ。というのも、もう三十年近い昔の話だが、会員になっていたスポーツジムのインストラクターに酷似している。彼女に違いない、既に私はそう確信していた。私はそのインストラクターに好意を持った記憶はない。それでも、見れば見る程、彼女だ! いよいよ確信するのだった。
事務所にはあの男一人で行ってもらうから、あなたはわたしと一緒にお風呂に行きましょう、私の胸元に触れるくらいまで近づいて、下から見上げながら彼女は笑みを落としている。
すべてが消えていた。インストラクターだけが臥せったまま上体を弓なりにそらせ、まだ私を見つめている。私の汚れた両足を、彼女の両手がぬぐっている。黒いゴミが詰まった足の爪からそれをほじくり、あなたをキレイにするわ、私の足の親指を彼女の親指と人差指と中指でつまんで、そうささやいている。