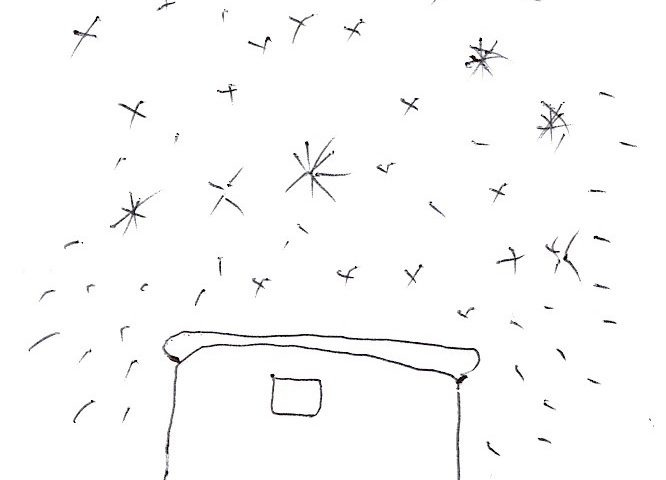月のひかりの降りそそぐ屋根の下
明るい窓の中から
子供の影絵が歌をうたってくる
さっきまで台所の暗い水の底で
こつこつまな板を叩いていた手を止めて
どうやらおかあさんは六月の夜にふさわしく
しんと聴きほれていたらしい
子供はひとりかいやふたりだ
すると急ににぎわしくなって
これは何んという星あれは何んという星
かえるの歌やら森の歌やら遠い旅芸人の歌やら
おまけに古めかしい物語の主人公まで飛び出してきて
四角い窓からアスファルトの道へ駆け抜けていく
もうじき仕事を終えたおとうさんの影絵も足音を
こつこつ響かせながら帰ってくる頃だ
子供たちの夢の歌が
水脈のようにひとすじ運ばれてゆく
夜の道を
*一九七九年六月十日、日記帳に書いていた詩。私は三十歳だった。