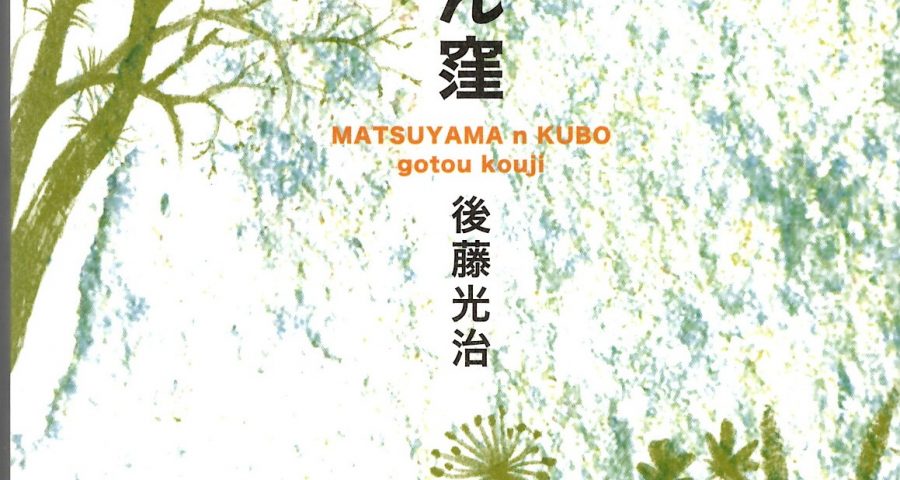まだ一面識もないが、私はこの詩人と互いの個人誌―彼は「アビラ」という個人詩誌を運営しているーを送りあっているので、まるで旧知のごとくおつきあいしている。その彼からこんな詩集が送られてきた。
詩集「松山ん窪」 後藤光治著 鉱脈社刊 二〇一八年三月一日初版
この詩集は三章で構成されていて、各章にそれぞれ八篇の詩が収められている。この詩集を理解するために、私はまず書名になっている「松山ん窪」(マツヤマンクボ)とは何か、ここから始めたい。
ここは高台の村の墓地
村人は「松山ん窪」と呼んでいる(作品「松山ん窪」9~10行目、本書24~25頁)
ここで、「松山ん窪」は、村の墓地で村人たちは先祖代々この墓地で眠っていることが明らかになっている。
「松山ん窪」は村の墓所
高台にある土葬の墓地だ(作品「命日」第3連6~7行目、本書35頁)
ここでは、村人たちは幾世代にわたって土葬で眠り続けていることが書かれている。ここは重要なところで、次の詩で土葬が火葬に変わったこと、否、私の記憶するところでは戦後の国の政策によって変えられたのではなかったか。
青く澄み渡った晩秋のある日
墓地の移転が行われた
高台の土葬の墓を掘り返し
火葬の墓所へ移すのだ
幾世紀も続いた墓地が
今日を最後に消えてゆく(作品「父」1~6行目、本書38頁)
この高台がある村は、「吹毛井」(フケイ)という著者の故郷で高校を卒業するまでここに住んでいたということだが(本書「あとがき」参照)、この村が土葬から火葬になった。これは戦後日本が核家族化していく一つの象徴ではないだろうか。言葉を換えれば、日本に住む一人一人が幼い時から晩年まで地縁で出会った人々とともに生きていく世界が消滅した、その象徴ではないだろうか。
おそらく著者は絵の心得があるのだろう、彼が生まれた幾世紀もの生命の連続体、そして今はコンクリート化した「失われた村」(作品「鵜の石」、本書70~73頁参照)を自然主義の絵画的表現に近く、緻密にかつ抒情的に描いていく。少年時代を生きた村と海、岬、空、星、その土地に住む人々のさまざまな姿がパノラマのように著者の脳裡へ迫り、それを言葉でていねいに復元していく。失われた日本の村の原風景とそこに住む人々の情を表現する貴重な一冊だった。