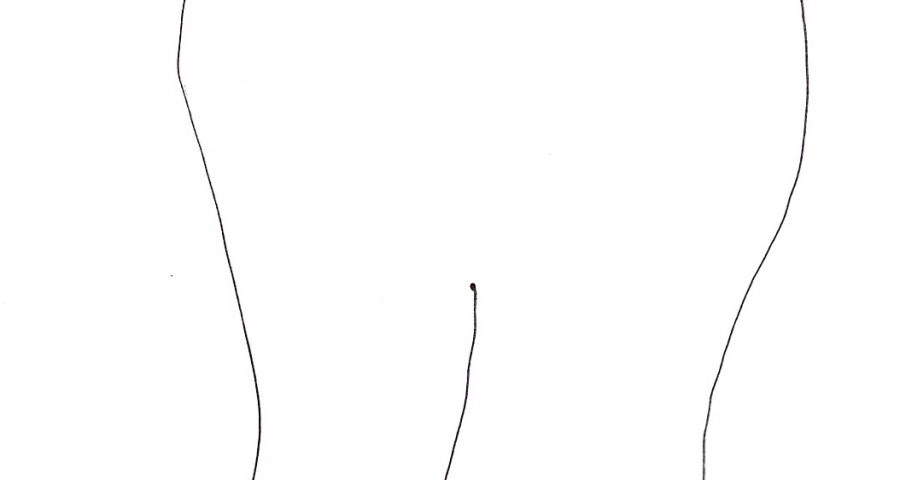外では雨が激しく降りしきっているようだった。
ふたりの体が隠れるか隠れないか、そんな小さな蒲団にくるまって、わたしはあなたと裸になって抱きあっていた。枕もとに座って灰色の服を着ているあなたが、裸になって夢中に愛しあうわたしとあなたを、じっと見おろしていた。全体が水の中の出来事のようにボンヤリ不透明だった。蒲団の隙間から覗くあなたの乳房が水に揺れていた。
兄だけではなかった。確か母も部屋に入ってきた。私はあわてて蒲団の中で着衣すると、裸になったあなたを残したまま、灰色の服を着たあなたの手を取って、スーッとその部屋を出ていた。しかし、フスマを開けると、あなたの手が消えるのがわかった。
廊下には父が立っていた。あたりは急に暗くなって、フィルムがプッツリ切れるように、途絶えた。
闇のリビングに、一部分だけが光っていて、高さ一メートルくらいの木の模型が置かれていた。その枝には白っぽい綿でかたどったのではないか、そんなオオムが顔を太い墨で描かれて止まっていた。鳴かなかった。ひっそりしていた。また、人の気配もなかった。
足もとの闇の中で、わたしは何かグンニャリしたものを踏んでしまった。しゃがんで、目を凝らした。白と黒とでまだら模様になったイタリアングレーハウンドに似た子犬だった。愛撫しようとしたら、飛び跳ねてわたしの手からその犬は逃げた。おびえた顔だった。
闇の原因は知れた。わたしは四重になったカーテンを一枚一枚開いていた。窓から、カーテンに閉ざされた隣家の窓が見えた。