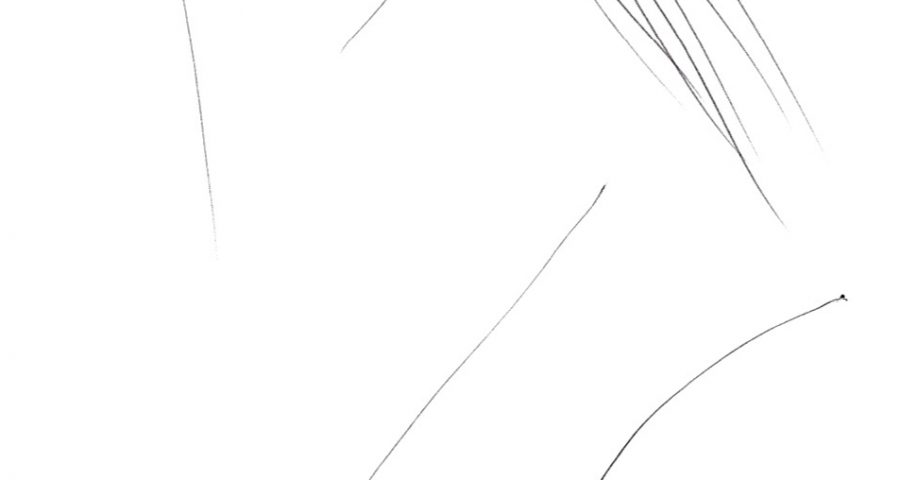昔、かなり親密な取引があった建築会社のオーナー、もう三十年近く音信が途絶えているが、彼とまた新たに取引が始まっていた。
すでに彼の会社は息子の代に変わろうとしている途上だった。時代は、AIまで導入して人件費を限りなく最低賃金に向かって操作し、何とか利潤を追求して企業を維持せんとする社会状況になっていた。従って、彼は、とりあえず彼をXと私は呼んでおくが、息子を一流のオーナーへと育てるために、あらゆる努力を惜しまず積み重ねていた。
ある日、Xの主催するセミナーに私は招待された。その席で、彼が期待を寄せている若い男性の研修生Aを紹介され、懇意になった。セミナーが終わると、「Xが経営するレストランに行って、食事でもしながら歓談しませんか」、そんなAの申し入れに私は首を縦に振ってうなずいた。
確かにAが言う通り、成長期から衰退期へ移行した現在のAI時代を反映して、それでもこの時代を生き抜かんとする強い意志が表れた、奇妙なレストランだった。中央のガラス張りになった厨房はまぶしいくらい明るく十人前後のシェフが忙しく立ち働いており、しかし、客席はおそらくかなり広いのだろうが、人影さえ確認できないくらい闇に沈んでいる、いわゆる省エネ型店舗だった。いつのまにか私は席についていたが、研修生Aの姿はなく、ぼんやり浮かんだ目の前のカウンターに大きなハンバーグを盛った皿が置いてある。ひょっとしたら、知らぬ間に研修生Aがすっかり変容していたのか、隣に席をとっているどこかAの面影をしのばせる、ほとんど胸をはだけた若い女性が淫らなまなざしで上目遣いに、「わたし、帰る切符代もないの。お金ちょうだい」、「いくらいるんだ」、「三千円」。私は財布から三千円出したが、「その三千円はあなたにあげる。財布をもらって帰るわ」、べっちゃり接触し私を抱き寄せながら、汁のように解体して私の中へ溶け込んでいく。
私は体中ねばねばになって、恍惚としていた。ベッドに寝ころんで天井を見上げたまま、私の頭の中は走馬灯になって映像と言葉が走りめぐっていた。……辺りはしんとしている。Xの顔だけが大写しになって浮かんでいる……今頃、何故Xと再会したのだろう、彼には娘一人で息子なんていなかったのに。陸上選手だったあのお嬢さんは、いま、どうしてるんだろう……そうだ、人づてに聞いた話では、一九八〇年代後半から始まったバブル期の投資で発生した巨額な負債の返済が出来ず、悪質な金融業者の追求から逃れるために彼はフィリピンに渡ったはずだ。だがその後、ひそかに帰国して、もう十七、八年前、六十歳そこそこで、大阪の下街で一人暮らしをしていたXは死去している。晩年になって、私は夢の中でそんな彼と再会したのだった。昔、一時、取引上でとてもお世話になった彼に、あの頃、若造で生意気だった私が言えなかったただ一つの言葉、「ありがとう」、そう言って彼と別れるために。