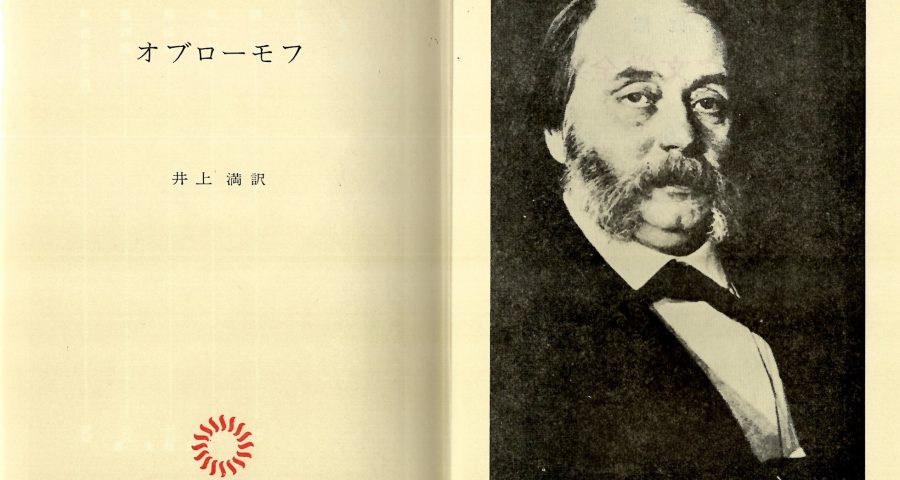この長編小説を読んでみよう、そう思ったのは、以前ローザルクセンブルクの所謂「ロシア文学論」(ローザルクセンブルク選集第四巻189頁以下参照)にこの著作が言及されていたからだった。何事もその裏付けを取っておく、私のそんなイヤな性格から、読もうとしたに違いない。そうは思ってみたのだが、なかなかこの本を開かなかった。そのあいだに、ひょっとして、私は倒れ、焼却炉からあがる煙になっていたのかもしれない。煙になっては、この本は読めなかったのではないだろうか。幸い、私はこの本の扉を開くことが出来た。
「オブローモフ」 ゴンチャロフ著 井上満訳 日本ブック・クラブ 1971年11月10日再販
この小説は一八五九年に発表され、ロシアの農奴制に支えられた地主の息子オブローモフの生涯を描いたものである。ロシアの農奴制はこの本が出版された数年後、一六六一年に廃止されている。しかし、資本主義的自由主義と帝政ロシアとの亀裂は深く、農奴制が廃止されたとはいえ、専制は引き続きロシアを支配し続けている。だからといって、この小説は当時の社会体制を批判したものではない。事実、著者ゴンチャロフはこの体制の優秀な官僚として生活を送っている。
確かにこの小説の主人公オブローモフは農奴から搾取した地代でのらくら生活して、現実には何も出来ない、無為徒食の男だった。そして無為徒食の飲んだくれとしてこの世を去っている。こうした意味では一見農奴制を批判した作品と言っていいのかもしれない。だが、著者ゴンチャロフはこの無為徒食者オブローモフを深い愛情をこめて描いている。つまり、どんな劣悪な社会状況、無意味な日々を繰り返している暮らし、生きる未来を失ってただ漫然と朝起きて食べて夜に寝ている、チャンスがあれば昼寝、著者はこうした生活を微細に描き出し、そこにも根底には愛がちりばめられている、それを証明せんとしているかに、私には思われた。どんなぐうたらな生活を送っていても、その底にはひとすじの愛が流れているのだろうか。